まなびしごとLABの風間です。
こんにちはー!
2025年2月14日(金)・2月15日(土)の2日間、筑波大学附属坂戸高校にて総合学科研究大会が開催されました。
今年もお声かけいただき、お邪魔してきました。
1日目(卒業研究発表)

1日目は3年生の代表者による卒業研究発表。
筑波大学附属坂戸高校の探究学習は、1年生が「産業社会と人間」という科目で探究活動の基礎となるスキル習得や自己理解を深め、2年生の「T-GAP」でグループ探究、3年生の「卒業研究」では個人探究を実施するというプログラムになっています。
この日は4人の3年生の発表を聴きました。
研究のタイトルを見ただけでも「うーん」とうなってしまうようなテーマです。
正直、なんでこんなテーマを思いついたんだろうと不思議なほどで、なかなか質問するのも難しいです。
でもそうしたテーマに「没頭」している様子がすごく伝わってきて、その姿や発表を見るのがおもしろくて、毎回楽しみになります。
また、自分もこのように没頭したくてたまらなくなります。
生徒さんたちが研究大会の運営や進行を担っているのもすばらしいですね!
今回も非常に刺激をいただきました。
筑波大学附属坂戸高校の本ができました!
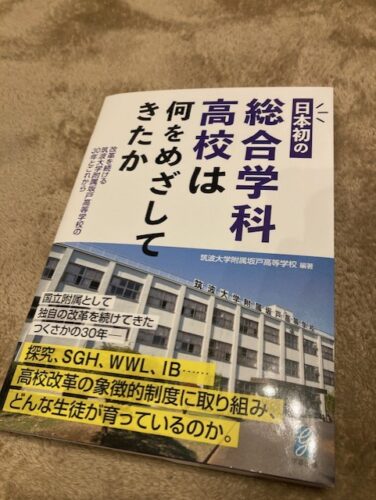
筑波大学附属坂戸高校の30年間の学びが本になったそうです!
タイトルは「総合学科高校は何をめざしてきたか」
同校のこれまでの歩みや探究へのこだわりがよく理解できる内容で、イチ筑坂ファンとして堪能しました。
ご恵贈いただき、ありがとうございました!
2日目(講演)
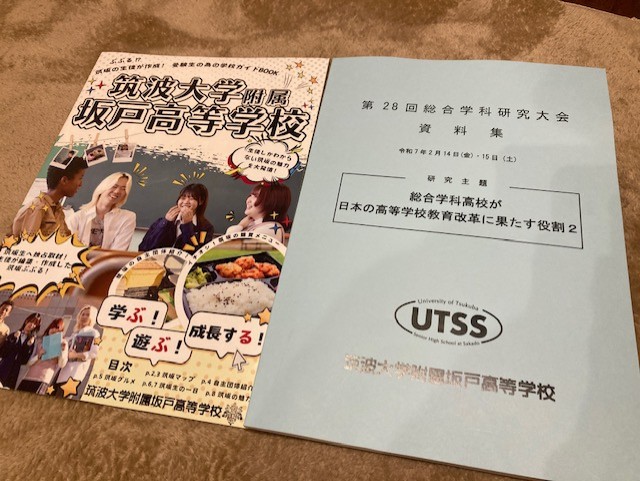
2日目はアジア学院校長の荒川朋子さんによる講演「共に生きるって、どういうことだろう」に参加しました。
すごく考えさせられたので、以下、備忘録として書き留めておきます。
・創立50年以上で、これまでに63か国1445人が卒業
・ほぼ自給自足で、学生は寮での共同生活を送る
・ルーツは農村伝導神学校(東南アジア農村指導者養成所、1960年開設)
・創設者 高見敏弘氏「宗教の壁を越えた真の対話による人間性の回復」
・素の自分を出して、ありのままで他者と対話することで、人間性を回復していく
・人格とは「本来の姿」
・国際化とは「国家、民族、人種、言語、数強などの相違を互いに乗り越えて、相違を互いに尊重し、美点を守りながら人間としての交わりを求め構成で平和な世界の実現を目指して、互いに努力している状態。異質の文化背景を持つものたちが、人間同士共に生きるために努力をし続けること」
・アジア学院が目指すもの「共に生きるために」
・共に生きる3つのポイント
①違いを知る
②共通点を知る
③自己変革(人間開発)の努力をし続ける
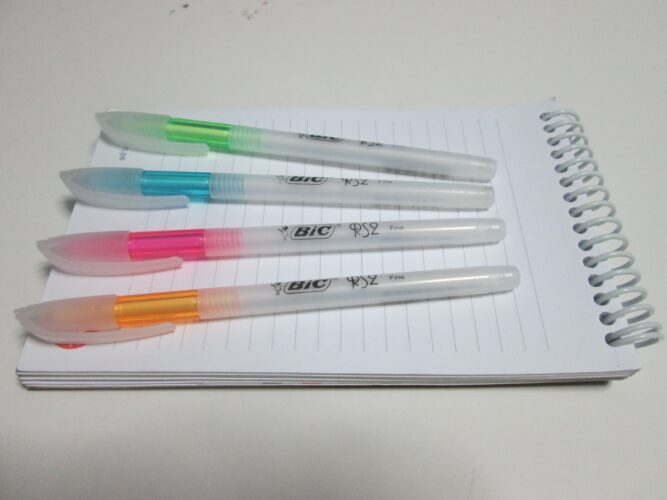
①違いを知る
・時間厳守は必ずしも絶対の価値観ではない
・時間は守れる類のものではない
・生徒たちが生きる社会では、時間厳守を阻む要因があまりにも多い
・大事な作物、家畜が病気になる、天災が起きる
・周囲の人や環境がそれだけ強い
・時間は自分だけの都合でコントロールできるものではない
・それが彼らにとって当たり前の感覚
・それらの違いを知ること、その背景を知ろうとすること
・歴史的背景、経済的格差、文化の相違
・なぜそういう違いがあるのかを考えるきっかけ
②共通点を知る
・きっと同じという期待があるから違いを感じる
・アジア学院で1ヶ月過ごすと国、民族、言語の違いは気にならなくなる
・その人自身の人間性の方が重要
・人間共通の道徳観、笑い、悲しみの理由
・見た目や育った環境が違っても、同じ人間
・命と食べ物はすべての人間にとって最重要課題
・必ずお腹がすく、食べ物を食べると満たされる
・一緒に食べると打ち解ける
・食べ物を持続的に安全に作り続けることはどこにおいても最も基本的で最も重要なこと
・共通点を知る=協働できる
③自己変革(人間開発)の努力をし続ける
・どのように自分が変革していくのか
・自分と違う人と一緒に生きるには、自分自身をしっかり受け入れることが大前提
・なかなか自分を受け入れられない
・固定観念、経済的制約、尊厳が損なわれている・・・
・自己変革と人間開発が必要である
・それを効果的に、効率的になすのはカルチャーショック
・カルチャーショックは「人間を文化的に桎梏(しっこく)、束縛から解放する力を秘めている」
・その時に自分にどんな変化を感じたか
・拒否、異質なものに触れてショックを受けた自分は、既に別の自分になっている
・人間は変化する環境に応じて変革する能力を本質的に秘めている
・近代化や開発が破壊するものは何よりも人間である、人間が自ら人間であることを放棄している(高見)
・「人間性を開発する」
・「人間性の最も善いもの、最も美しいものはすべての人の中に秘められている。それを十分に成長させることである。これが人間開発の真の意味であろう。人が人となるための人間開発である」
・自分自身を愛しているという地盤がしっかりしていれば、どんな環境の変化があっても受け止められる
・その上でカルチャーショックをたくさん経験する中で、自分の人間性を開発し、成長すること
個人的には「自己変革」というワードが非常に印象に残りました。
しかもこの変革は1回限りのものではなく、「変わる努力をし続ける」ことが大事であるといいます。
これがまさに探究の目的になりうるのではないかと思いました。
貴重な気づきをありがとうございました!
キッチンカーでランチタイム

この日は地域の事業者の方を中心に、キッチンカーが何台も来ていました。
こうした地域との連携もすばらしい取り組みだと思います。

私は午後から別の予定があったため、「みんなでここdeごはん」さんでキーマカレーをいただいて帰りました。
キーマカレー、ごちそうさまでした!
おいしかったです!

メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。
前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。
サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。
地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!

